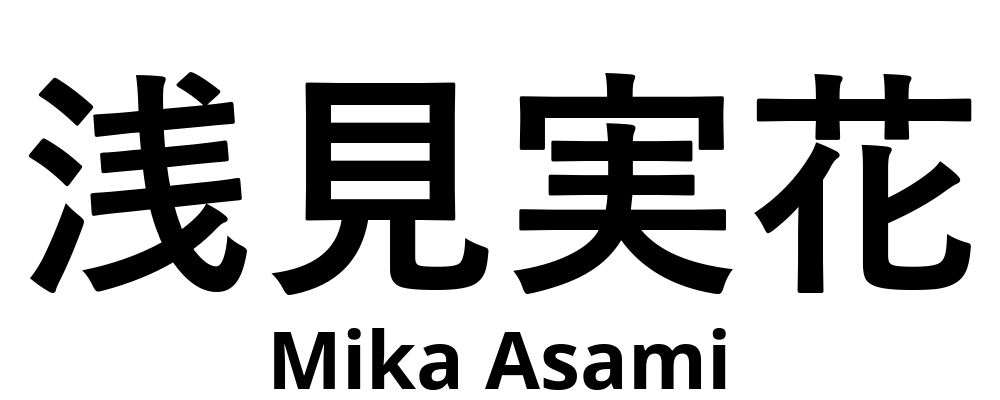車がなければ何もできないような環境なので、毎日車で移動している。
引越して3週間。いまだに暮らしに必要な手続きが入ってくるので、目的地とまわりの地理を覚えつつ、ちょっと道草したりしている。具体的には、気になる場所で車を降りて、カメラでカシャっと記録する。とくに明確な意図はないが、自分にまだ”よそ者”の視点のあるうち、この土地の気になるものを断片的に記録したいという気持ちはあるのかもしれない。
昨日はこんな風景だった。

幹線道路を外れると、もうこんな畑の真ん中にやってくる。

キャベツ畑とレタス畑とスプリンクラー。


ジュリアン・バーンズ『終わりの感覚』にこんなことが書かれていた。
いったい歳を取るとはどういうことだろう? 若いあなたはひょっとするとそれを予測し、想像することができるかもしれない。人生が終盤に近づいたときの感覚。子どもたちが去っていき、友人も少なくなり、社会的な地位が下がり、欲望は減退し、欲望の対象からも外されていく。しかしそれも、あなたがただ先を見ているにすぎない。
「ある未来の地点から過去を振り返るとは、どういうものか?」これは若いあなたには想像がつかないものだ。時間はあなたに新しい感情をもたらす。歳を取ると、あなたの記憶はおぼつかなくなり、自分がだれで、どんな人間であったのかという確信が薄れていく。たとえあなたが言葉や音や写真を使ってどんなに記録を取ろうとも、結局あとになってみれば記録のしかたが間違っていたのだと思い至るかもしれない。それは「歴史とは、完全な記憶がなく、十分な記録のないところに生まれる確信」だから。
なるほど、そいうこともあるかもしれない。
まだ若い人たちは、老年になった自分がどのように人生を振り返るのかがわからない。日記、音声、写真、映像。せっせと残したあらゆる記録があとになってどれほど役に立つのかも、私たちにはわからない。どうしてこれを残したのか? なぜそんなふうに見えたのか? 長い歳月のもたらす新たな感情によって、たとえ同じ事象についても、いつかの自分は当時の自分とまったく異なる反応を示すことになるかもしれない。
あるいはこの小説のように、人生も終わりに近づいた頃、忘れ去られた記憶や記録がよみがえり、もう自分にできることはないのだと静かに打ちのめされることだって、場合によってはあるかもしれない。暗闇の中で必死にサーチライトを回すような。いかんともしがたい混沌へ放り込まれていくような。
しかしそれでも、多くの人は記録を残す。残そうと努力する。いま見つめているこの光景。聞こえてきたあの音、あの声。触れたばかりのその言葉。それらを忘れないように。それらをつなぎとめるため。それらを自分に取り込んで、注ぎ足していくように。
小説『終わりの感覚』は、「累積」「責任」「大いなる混沌」で結ばれていた。そこで抉り出されてきたものは、欠けた記憶と欠けた記録の交差する影の側。そこから起きる負の連鎖だ。
ならば光のサイドとは? この物語が1つの真実であるならば、また別の真実も存在する。
「しかしそれでも、多くの人は記録を残す。残そうと努力する」ーーー個人的にはそこのところをやっぱり信じていきたいな。