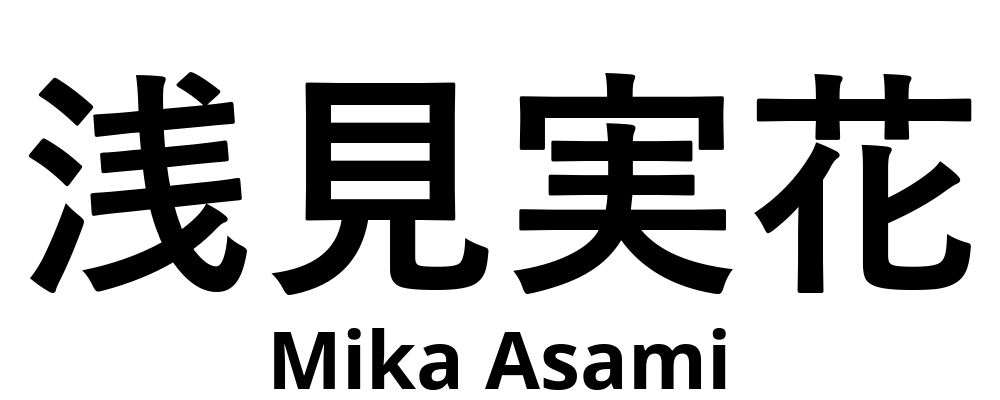誕生日がきて、また1つ歳をとった。母のお腹からストーンと出てきて、もうこんなに月日が流れたんだと思う。長いような、短いような。ひとつひとつの思い出を取り出すと、ずいぶん前のようでいて、ときどき妙に生々しい。年を追うごとに、時間が過ぎる感覚がよくわからなくなっていく。いわゆる脳科学的には、歳を取れば取るほど時間がより速く過ぎるように「感じる」そうで、それを聞くと老年ってどんなになっちゃうんだろうと、そら恐ろしい。毎年思うけど、自分が何年生きたという感覚はあやふやで、多分これからもピンとくることはなく、気づけば歳の数が増えていき、かといっていい歳になっちゃうので、それなりの落ち着きを装いつつ、内心では戸惑ったり、ショックを受けたり、そうかそうかと自分を納得させようとしたりするんだろう(だって○○歳なんて、すっごい大人というか成熟してると思ってたよ? なのにこれ、これでいいの、まあ、こんなものなのなのかねえ…?)。
寝室の収納を開けたら、母が自分を産んだときの手記が目に入った。母子手帳ではなく、市内の小さな産院でもらったであろうノート。おととし急に母が亡くなり、遺品整理をしていた父が埃をかぶっていた手記を見つけ、おまえが生まれたときにお母さんが書いたものだ、と渡してくれたのを、しばらく読むことができないでいた。ノートを手に取り、たぶん今は大丈夫だろうと思った。一周忌も過ぎ、ある程度落ち着いたから、と中を開いた。
よく知っている母の字が走るように並んでいた。つらい気持ち、悲しい気持ちもやっぱりどっと寄せてきたが、不思議な感じもあった。そこには現在の自分よりひと回り近くも若い、30にもならない母がいた。もちろん昔の写真を掘り返せば、若かりし日の母はいつでも見れるけど、写真には姿しかうつらない。ちょっとした表情から母の気持ちは推測できても、ほんとうはどう思っていたのか、何を考えていたのかは教えてくれない。だから出産手記を開いて、当時の母に、たとえ向こうは私のことが見えなくても、こっそり対面しているような気持ちになる。
予定日を2日過ぎ、待ちに待った陣痛がきた、と書いてあった。早朝から陣痛の時刻が、何時何分、何時何分と正確にすべて記録してあった。相当いっぱいいっぱいだろうに、走り書きでも流れるようなきれいな字だった。いつもすらすら美しい字を書く人だったと思う。それから産院へ行ったこと、陣痛や出産のいきみがとても辛かったことが書かれていた。ただでさえ我慢づよくて、大変なことも大変だと言わない人、あとになって中年で大病をして、弱音も吐かない人だったのに、「辛い」とあった。それでも「お腹の子はもっと大変な思いをしているんだから頑張らなきゃ」と書いてあった。そこを読んだらもうなんだか、こみ上げてくるものがあった。おかあさん、私そんなの一切わからない、全然平気だから大丈夫だよって言ってやりたい。まだ私よりずっと若くて、頼りなさ、インセキュアな雰囲気をたたえていて、私より繊細で、おそろしく忍耐づよくて、つい誰かのために無理してしまう、人のために力を振り絞って奉仕してしまう母に、私は穏やかに堂々と言ってあげたい。大丈夫だから安心していいと言ってやりたい。体、華奢なのに、そんな頑丈じゃないのに、心配や不安でいっぱいだったろうに、ほんとに辛かったね、お疲れさまだったねと、心から言ってあげたい。出産の恐怖は絶対にあったはずで、その前の9ヶ月間も、それから産後の初めての私のお世話、育児のこと、家庭のこと、家族関係のこと、そういうことがずうっと続いていって、どうしていいかわからないことなんて山ほどあったよねって言ってあげたい。ほんとに産んでくれてありがとう、ありがとう、それだけでありがとうって伝えたい。私いまこんなだよ、お母さんの家族もこんなで元気にしてるよ、孫たちも元気だよって知らせたい。なんでいきなり亡くなったの、誰にも言わないで、突然、ひとりきりで、さみしい、すごくさみしい、みんなさみしがってるよって言いたい。みんな感謝してるんだよって言いたい。
言いたいことがたくさんあって、伝えなきゃ、伝える努力をしなきゃだめなんだってわかっていたのに、その人はずっとそこにいるって思ってたのに、現実は違ってる。ある日突然いなくなり、もう二度と会えなくて、ぽっかりといつまでも埋まらない空席ができている。
言いたかったこと。あの日の母に、もうここにはいない母に、言いたかったこと。