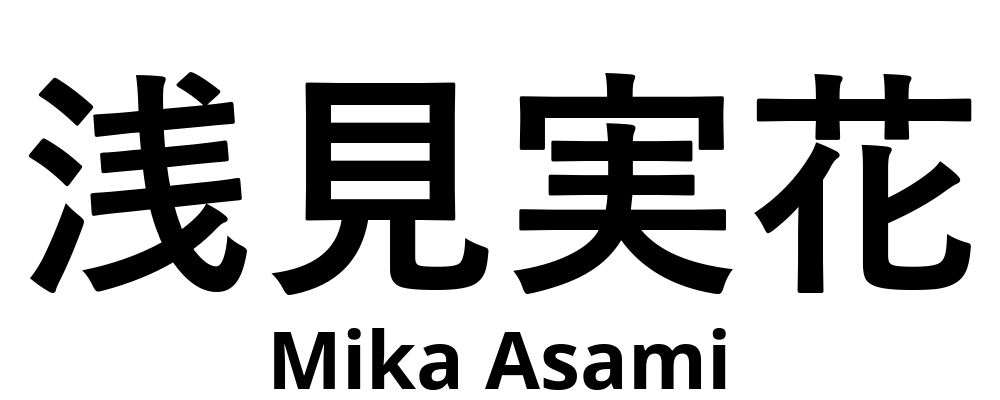今年はだいぶ春休みが長引きそうなので、平日は子どもたちと1〜2時間ほど、マイナーな場所でハイキングや登山をしている。(仕事もしてます)
平日の午前中、玄関先から目的地まで車で移動し、そこから歩いて登って降りて、家に戻ってくるまで、毎回だれにも遭うことがない。あたりは野山、ホーホケキョと鶯が鳴いている。
先週は、上田にある塩田城跡を登った。鎌倉時代に隠居した北条義政が居をかまえた館の跡で、現在は2時間あれば行って戻れるハイキングコースになっているが、あまりにもマイナーなため情報も多くない。限られた写真を見ると、一部に岩壁があるものの、子どももわりと気軽に登って歩ける印象だった。
登り口もこんな里山風景で、ちょうど桜も咲いていた。


最初は散歩道という印象で、だんだんハイキングになってくる↑

いつの間にか岩登りに発展するが↑
小学生たちもなんとか無事に進み、

上からの眺望をたのしむ↑
しかし、みんなで無事に登頂したあと、先の切り立つ岩も降り、あとはこのままゆっくり歩いて下るだけという頃になって、思いがけない事態になった。
張りきって先頭を歩いていた長男が、崖から10メートルほど転落したのだ。

ちょうど、こんな見た目の場所だったと思う。
すぐ目の前で、長男の足場が岩ごとガラガラ崩れ落ちた。「うわっ!!」と叫んだ瞬間、彼が崖から後ろ向きに回転しながら落ちていった。
わたしは声さえあがらなかった。人は心底驚くと、叫ぶことなんてできないのかもしれない。そもそも悲鳴をあげるには、大きく息を吸い込む余裕が必要になるからだ。ただこのとき、心の中で「うわああ」と思った。「は、嘘でしょ?! こんなところで長男を失うわけ?!」 一瞬で背筋が凍った。だから次は、この恐怖観念を掻き消すしかなかったように思う。「いや、助かる。ぜったい助かる……」 下へ下へ、どんどん小さくなる影を瞬きもせず必死で追った。「よーく見て、よーく見て!!」 わたしは上から、彼がどこにぶつかるか、どこまで落ちるかを見届ける必要があった。いざというとき医者にうまく説明できるように。
ーーー 数秒後、下のほうから怒りに震える息子の声が聞こえてきた。
「い、痛い! 痛いよー! クソ! クソ野郎!!」 最近不良漫画を読んでいたためか、これでもかとFワード(禁句)を連発している。夫はうしろのほうにいて、落下の様子を見ていない。わたしは声を取り戻すと、腹の底から大きな声で言った。
「よし、生きてる! おまえは生きてる! 生きていれば、だいじょうぶだ!!」
われながら惚れ惚れするような男らしい語気だった。よく慣用句で “火事場の馬鹿力” というが、局所的に自分のなかの父性性があらわになった。もしも下で大出血していたら、先のような息子の怒号はあがらない。とにかくいまはパニックを避け、安心させてやることが肝心なのだと確信した。それにどうやら彼のほうも、必死で自分を鎮めようとしているのらしかった。
「おー、おれは生きてる! おれは生きてる! おれは生きてる!」……
結果的に、息子はごくごく軽症で救われた。崖の下に谷はなく、落ちたところに大きな岩やするどく尖った木の幹も幸いなかった。意識も飛ばず、めまいや激しい頭痛もなく、ただ額の上のボールのようなタンコブと若干の流血だけでコトなきを得たのだった。
私たちは彼のところへ降りていき、身を寄せ合って水筒の水を飲み、泥をはらってゆっくりと城跡を降りていった。
「うわー、怖かったー、びっくりしたー、ショックだったー」 車の前でもう一度頭をなでると、息子はメソメソとすすり泣いた。
帰宅して夜、夫が噛みしめるようにいった。
「もちろんさ、彼が助かったから言えることではあるんだけど…… あいつにとって、今日のことは非常にいい経験になったと思う。ああいう危険に遭うのって、とても大事なことだけど、なかなか経験できないから」
無論すべては命あっての話だが、ほんとうにそう思う。思わぬ事態に遭遇したり、痛い目に遭ったりしないと得られない学びがある。人生なんて穴ぼこだらけだ。いつどこでどんな穴が、あんぐりと口を開けて待っているかはわからない。落ちるかもしれないし、落ちないかもしれない。心して前に進み、落ちたとしてもうろたえず、次に打つ手を考えながら、すばやく行動するしかない。そうして再び前へ進む。もっといい方法、もっといい準備、さらなる対策はなんなのか。Risk is a part of life. いくら世界とのつながりを断とうとも、どんなに安全と言われる場所に逃げこもうとも、大なり小なり常にリスクはそばにある。”リスク”と言うと、なんとなく危ないもの、全力で避けなければならないもののように聞こえるが、実はそれは”不確実な未来”でもある。
「だからさ、ま、これに懲りずハイキングに行こう。過度に恐れず、しっかり準備して、また楽しく行くんだよ」
この一件で、息子は注意深くあることの大切さを思い知り、みずからあちこち装備して、一歩一歩、また一歩、足を前に踏み出していく。