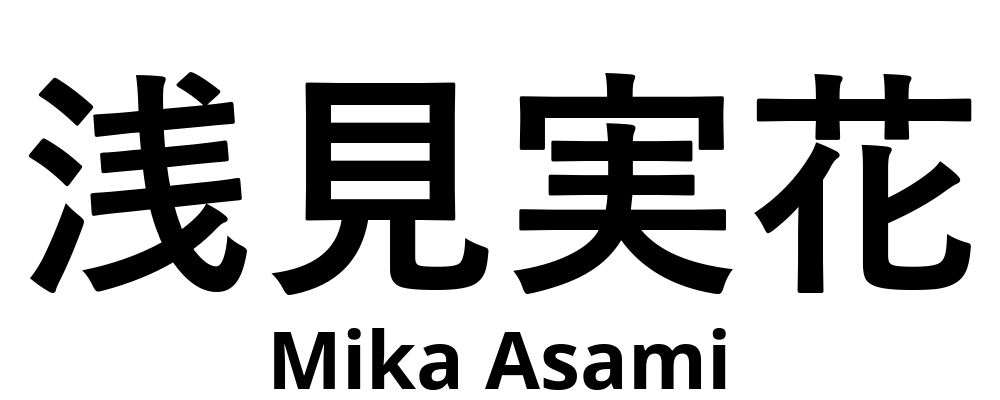インド・バラナシ・巡礼の町
火葬場とその周辺
インド・バラナシ・巡礼の町
火葬場とその周辺

「ところで、火葬場を見たいですか?」
ラジさんが聞く。
ここバラナシでは「火葬場」が特別な意味を持つ。
ヒンズー教徒のあいだでは、死後この町で遺体を焼かれ、その灰をガンガーへ流してもらうことにより、みずからの魂が天に昇ると信じられているためだ。
「そうですね、まだ幼い子どもがいるので。ちょっと近づくだけにします」
「そうね、お子さんたちには見せないほうがいいでしょう」

わたしたちは、巨大な薪がうず高く積まれた場所にやってくる。
薪はあまりに長いので、大の大人も運ぶのに苦労するほどだ。相変わらず野犬がちらほら目につくが、彼らはただボンヤリと辺りをうろつくだけ。
ふと、だれかが話しかけてくる。浅黒い、ずんぐりとした中年男性。
「どうか薪を買ってください。薪、たくさん必要です」
「薪?」
「そう、薪。この火葬場、インド中からたくさんの人、やってくる。この土地で死ぬために。老人、病人、けが人、たいへん貧しい人たち、衰弱した人、集まってくる。わたしの仕事、そういう人をホスピスに入れること。みんなここで死ぬのを待ちます。死んだらここで焼かれます。火葬場にたくさんの薪、必要です」
一般的に、ヒンズー教ではお布施や寄付が推奨される。寺院にたいする寄付だけでなく、生活に困窮する人びとや修行に励む行者らに進んでお布施を施すことは善行と見なされており、現世における自分の罪を浄めることにもつながっている。
郷に入っては郷に従え。わたしたちは手持ちのお金を寄付として彼に渡す。
「ありがとうございます。できたらもっと買ってほしい」
「今日はあまり現金を持ってきませんでした」
「もっと薪、必要です。どんどん人やってくる」
「現金がもうポケットにありません」
わたしたちは「もっと、もっと」とせがまれる。途上国を旅行したことのある人ならば身に覚えがあるだろう。
「もっともっと買ってほしい。あなたは豊かな国からきたのでしょう? この土地の品物をもっともっと買っていってほしい。この土地の人びとを助けてほしい」
ときに押しの強い相手の態度に、先進国の旅行者は辟易とするかもしれない。しかしこうして現地の人が熱心に勧誘するのは、それが彼らの仕事だからだ。彼らはこうして今日の食事、明日の食事を稼いでいる。あるいはわたしたちと同じように、家族を養っているのだろう。
いっぽうで、ただ望まれるままに「恵んであげる」ことだけが正解なのかはわからない。正解などどこにもない。
「いま渡せる現金はそれだけです」
「そう、わかりました」
勧誘は終わったようだ。
「ところであなたたち、これから火葬場を見たいですか?」
ずんぐりした彼が言う。
「いいえ、子どもがいるのでここまでで大丈夫」
「そうですか。火葬場は特別な場所。昨日、外国人観光客が火葬場にやってきて、禁止の写真を撮りました。全然言うこと聞かない。だから鞭で打たれました」
「鞭?」
「火葬場は撮影禁止。亡くなった人、遺体を撮るの禁止です」
鞭とはなかなか手厳しい。けれども基本は、郷に入っては郷に従え。いくら町にお金を落とす観光客でも許されないことがある。ここは亡くなった人が焼かれる火葬場であり、ヒンズー教の信者にとっては魂が身体を脱し、天へと昇る神聖な場でもある。
ここは人間の生命、生と死が交差する場所なのだ。
かつてイギリスが植民地としてインドを支配していた時代、この火葬場を町から離れた郊外へ移転させる計画が持ち上がったが、ヴァラナシの人びとから強い抗議を受けた結果、計画は中止となった。その独特の死生観を表す言葉が、ヴァラナシの公文書館に残っている。
火葬場は町のために存在するのではない。町が火葬場のために存在するのだ。
現代のように海を越えた限りない人の移動、巨大なグローバル・ツーリズムが世界へ隈なく拡がる時代、ローカルな文化や習慣、現地で暮らす人びとに敬意を払えない者は、追い出されても仕方がないのかもしれない。
わたしたちは火葬場を後にする。

喉が渇いてきたので、道端でチャイを買う。
チャイというのは、水で紅茶を煮出したものにミルクと砂糖を入れ、さらに煮出した庶民の飲み物だ。イギリスの植民地時代、型落ちしたダストティーを活用したのが始まりらしい。現地の水でもじゅうぶんに沸騰させているので、たぶんお腹はだいじょうぶ。
ボロボロの掘建小屋に腰を掛け、熱々のチャイをすする。
「これ、おいしい!」
「すっごく甘い!」
砂糖いっぱいの温かな飲みものは、子どもたちにも大人気だ。

Photo: Aditya Chinchures
引き続き、ガンガー近くの路地を歩く。
街角のちょっとした木の根もとや像の前で、現地の人が立ち止まり、花やろうそくを供えていく。こういうところも神社や祠、お地蔵様やお稲荷様に手を合わせる日本人の精神性や習慣にどこか通じるものがある。

ところでこれは ↑「リンガ」と呼ばれる崇拝の対象で、ヒンズー教の寺院の中や街角のあちこちに地味ながらひょっこりと顔を出す。
実はこれがシヴァ神の象徴で、男性性器のシンボルでもあることは、なにも知らないわたしたちを一瞬ドキッとさせる。しかもその根もとにあるのが女性性器のシンボルなのだ。
バラナシ大学で日本語を学んだという現地ガイド・ラジさんが教えてくれる。
「インド人がリンガを崇拝するとき、そういう意識はもちろんないです。そういうことは一切ない。子どもの頃から自然に拝んでいますから」
では、いったいどんな意識があるのだろう。ひとたび事情を聞いてしまうと、リンガを見るたびどことなくそのことが意識にのぼってしまいそうだが———
「すべてはここに始まり、ここに終わる。そういうことです」
なるほど、ラジさんがシンプルな言葉でまとめてくれる。
シンプルだが、また本質的な説明だ。世界の創造という概念が、男女のシンボルが結ばれることにより堂々と表現されている。この土地の人びとは、あちこちで祀られるリンガの向こうに、世界の創造、宇宙の成り立ち、生命の真理をボンヤリと感じつつ、またそれを取り立てて意識せず、ただひたすらに日常的な習慣や様式に落としこむことにより、世代を超えて大事ななにかを引き継いでいるのだろう。
このような、あまりにも素朴かつ根源的な性にまつわる崇拝は、現代の日本で暮らすわれわれをどこか面食らわせるところがある。それはわたしたちの社会というのが表向きには性をタブー視するいっぽうで、隠れたところでそれが盛んに消費されるありさまを黙認するような面があるからなのかもしれない。


「ねえ、さっきガイドさんはなんて?」
「うん、あれはね……」
子どもたちもいつか創造の神秘について学ぶときがくるだろう。
気を取り直したわたしたちは、バラナシ最大のヒンズー寺院「カーシー・ヴィシュヴァナート寺院」を目指す。
ガイドのラジさんとはここでサヨナラだ。

火葬場とその周辺
カーシー・ヴィシュヴァナート寺院
食べもののこと、河畔のテラス
デリー行きの夜行列車