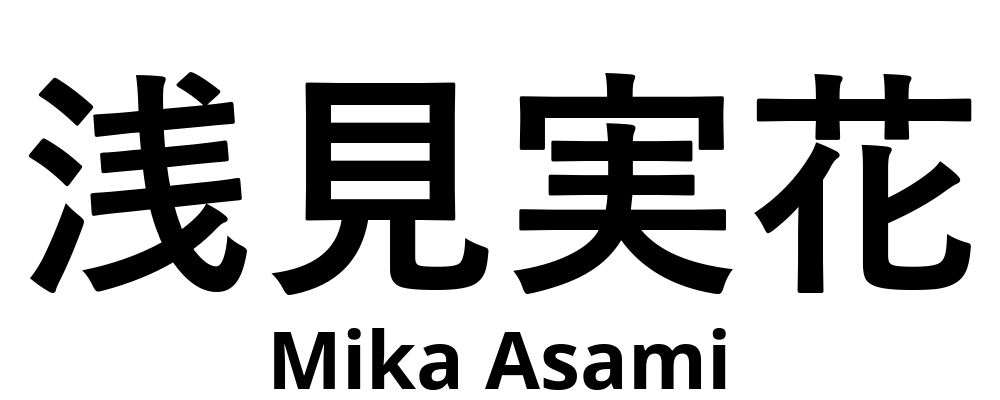「ああ、カズオ・イシグロがいる……」
先週の日曜日。私のすぐ目の前、ほんの4〜5メートル先にカズオ・イシグロが現れました。
おそらくは奥さんをともなって、ロイヤル・フェスティバル・
私はちょうどイシグロとオンダーチェのトークイベント「Kazuo Ishiguro & Michael Ondaatje」(ブッカー賞50周年関連企画)

ところでこの「ロイヤル・フェスティバル・ホール」、
「サンスバンク・センター」は欧州でも最大規模の芸術複合施設(
だからもうサウスバンクにやってくると、
現代の日本人には想像しにくいかもしれませんが、




そんなわけで、カズオ・イシグロとマイケル・
じっさい生身のイシグロさんは、
長年の友人であるイシグロ氏とオンダーチェ氏は、
トークは(おそらく敢えて)あまりストラクチャーされていない構成で、オンダーチェさんの好きなコラージュからスタートしました。
オンダーチェ:
コラージュが好きなんだ。コラージュが何かっていうのはよく知らないんだけど。いろんなものを、対立するアイディアも含めてすべて混ぜ合わせる。そういうことがコラージュではできるからね。1つの本みたいに。そういうアートのフォームが好きだよ。
それからふたりの幼少期の白黒写真(カワイイ!)
ちなみにイシグロさんというと、日本の主要メディアはつい日本人としてのつながりに目を向けがちなのですが、
以下、いくらかメモです。
イシグロ:
ぼくは記憶に興味があって。それを第一人称で語るナレーターがいるっていう。ぼくとしては30年前のできごとも、 3日前のできごとも記憶の中で流れるように紡いでいきたいと思っ てるよ。それはまあプルースト的ってことになるんだけど。
イシグロ:
ほかのアートのフォームにはよく嫉妬を感じてしまうよ。小説ではやりにくいことがあるからね。たとえば音楽なんかには。
現代アートも、なぜそれをするのかがそこまでロジカルに説明されなくていいっていうか、より直感的だという印象を個人的には受けるよね。ぼくのほうはそれを説明できなきゃならないんだけど。
イシグロ:
5歳でイングランドに来て、9歳くらいからだんだん本が読めるようになっていった。友人の家に行ったら、その家の書斎にたくさんのペーパーバックがあって。それに興味を持ったのを覚えてる。そこがぼくの本へのアクセスになったんだ。あの頃ぼくはまだ世界について何も知らなかったので、当時の読書はまだ理解が半分くらいの状態で。いまでもあの読み方を懐かしく思っているよ。もうそういう読み方ができないからね。いまでは本をジャッジできてしまうから。よくわからない世界の中で、どこか霧に包まれたような読書という体験を、ぼくはとても楽しんだ。自分の小説で読者を迷子にさせることはできないけれど、そういう感覚は読者の人にも分かってもらえたらいいなって思ってる。
イシグロ:
ぼくが興味のある本はノンフィクション。フランス人のお気に入りのノンフィクション作家がいて、彼女は「対立」の起きている世界のさまざまな場所を旅しながら書いているんだ。ルワンダだとか、アパルトヘイトの後の南アフリカ、人種的対立のあとのアメリカなんかを。これはぼくにとって大切な問いを立ててくれる。つまりそれは、社会や国家、ぼくたちは、この世界で起こったことをいつ忘れられるのか、あるいはいつまで覚えているのか、そういうことだよ。
イシグロさんのお話を聴きながら、私は「浮世の画家」を思い出していました。どこかの記事で読んだのですが、イシグロさんが記憶にかんするプルースト的アプローチを思いついたのは、彼がまだ駆け出しのライターで、体調を崩してベッドで数日ゴロゴロしていたときのことだと言われています。彼はまさに「そうだ、そうなんだ」という具合に、はっきりとその可能性に気がついて、なにかをすとんと理解した。ベッドの上で、どうもそういう瞬間があったらしいです。「なるほどな、そういうふうに書いていけばいいんだ」と。
「浮世の画家」を読むと、読者もこの記臆間のなめらかな移動というのを体験すると思います。いつの間にかそこに連れて行かれて何かをいっしょに目撃し、ふと気づけばもといた場所に立ち戻って、またつぎの何かを予感しているというような。
「日の名残り」はブッカー賞受賞もあって世界的に有名な小説ですが、その映画版(米英共同制作)もここではかなり評判がいいらしい。主演はアンソニー・ホプキンスとエマ・トンプソンのふたりです。これはまた今度見るのを楽しみに。
最後にサウスバンク・センター内、ロイヤル・フェスティバル・ホール周辺の雰囲気を記録します。
ロンドンにしてはめずらしく、1ヶ月以上も夏日が続いています。