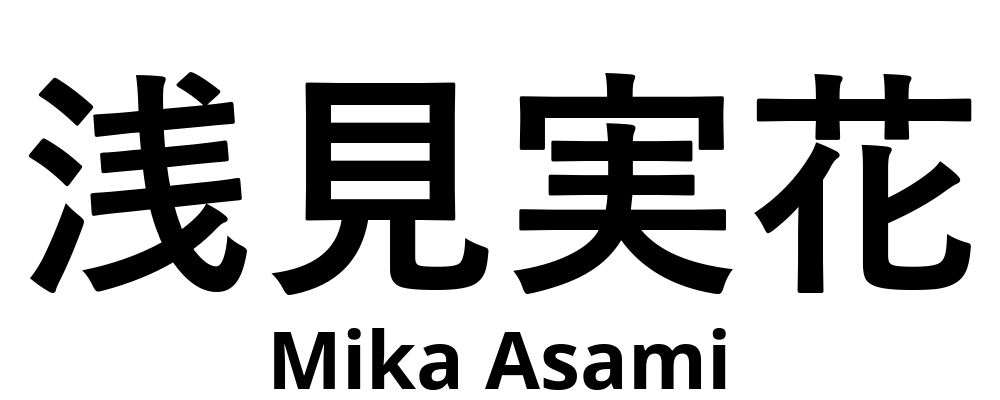アフリカへサファリに行く
マニヤラ編(1)
アフリカへサファリに行く
マニヤラ編(1)
アルーシャの町からサファリがはじまる
東アフリカ。タンザニア。
一台のプロペラ機がアルーシャの空港へ降り立つ。

乗客は、パイロットを含めてたったの7人。正直これほど小型だと思わなかったが、アフリカの国内便はプロペラ機が主流らしい。
ロンドンからここに来るまで、飛行機を2回乗り換えた。まずアディスアベバで乗り換えて、ザンジバルからタンザニアへ入国、それからこのプロペラ機に乗り込んで、サファリの始点と呼ばれる町、アルーシャにたどり着いた。
はじめて乗ったプロペラ機には、予想以上に面食らった。
さいわい機体は安定しており、身の安全に恐怖は感じなかったが、そこで見た景色には意表を突かれっぱなしだった。なんというか、視界に入るあらゆるものが既知の枠からずれている。
まず操縦席が近すぎる。大柄な白人のパイロットは私の目の前、手をのばせば触れられる場所にいる。操縦士の画面さえこちからは丸見えで、それがあまりに頼りないのにおどろかされる。つぎにあたりを見回すと、機体の壁や扉のあたりが古めかしいのが気になり出す。後ろの荷物置き場はカーテンが破れていて、まるで布切れが宙をゆらゆら漂うよう。しかたなく窓の下へ視線を移すと、そこにはもうエメラルドとブルーに染まったインド洋が広がっていて、それがまたこの世のものとは思えない不思議なオーラを放っている。しかたなく視線を戻すと、今度は操縦士の頭の向こうに、雲をずんと突き抜けたキリマンジャロが、まるで巨大な門番のようにじっとこちらを見つめている。
この異質さはなんだろう?
–––––なるほど、私は本当にアフリカにやってきたのだ。




無事にプロペラ機を降り、がらんとした空港を通り抜ける。
空港の出口の前に、一台のサファリカーが止まっている。 トヨタのランドクルーザーをサファリ仕様にした車。スーツケースを転がしながらキョロキョロしているアジア人の姿を見つけ、運転席からだれかがニコニコ降りてくる。現地のサファリ・ツアー会社から送りこまれた、案内役兼ドライバーのシンバさんだ。
「ジャンボ(こんにちは)! ガイドのシンバです。ライオン・キングは知っている? あれに出てくるのと同じ『シンバ!』だよ」
屈託のない笑顔がいい。底抜けに明るいのも、すごく人懐こいところも。ガイドにはぴったりの人柄だろう。
「僕は動物が大好きなんだ。これからいっしょにいろんな動物を見て回るよ。どうぞよろしく」
握手をすると、ツアー会社のロゴが入ったTシャツを渡される。シンバもすでに同じものを着込んでいる。
「よかったら、いっしょにどうぞ」
おそらくは中年だろう、どうしてもアフリカの人びとは年齢不詳に見えてしまう。私は服の上からもう1枚、もらったばかりのTシャツをかぶる。
「うん、いいね。そうそう、僕らはチームなんだ」
だしぬけに出たチームの言葉がすぐに飲み込めない。いまはじめて会ったばかりのすごく陽気なアフリカ人とチームを組むということが。でも、言われてみればたしかにそうで。
私はここがどんな場所かをまったく知らない。ふだんずっと都市にいて、その機能に護られている者が突然サバンナを訪れる。目的はサファリ観光。野生動物見物だ。
「ねえ、ちょっと、あなたたちの姿を見せてくれない?」
サバンナにはさまざまな野生動物が生息している。もちろん肉食動物も。ライオンやチーター、ハイエナがすぐそばで歩いたり寝転んだり、あるいは狩りをするかもしれない。どのガイドブックを開いても、車の外にはぜったい出るな、と書いてある。さすがに車内は安全だろうが、寝泊まりするテントのまわりはどうだろう?
それに、危険なのは肉食動物だけではない。ここにくる前、病院でトラベルワクチンを打ってきた。破傷風、チフス、A型肝炎、B型肝炎。両腕では収まりきらず、お尻もプスッとやってきた。1日1回マラリアの予防薬を服用し、病気を運ぶハエを寄せ付けないように明るい色の長袖と長ズボンを身につける。それでも、もし体調を崩したら? ケガをしてしまったら? 私が最初に頼みにするのはシンバさんになるだろう。この4日間、私たちはサバンナで行動をともにする。もしも彼になにかあったら、その役割は逆転する。しばしの間、私たちは1つのチームというわけだ。
かろうじて舗装された、太くて長い幹線道路をサファリカーがビュンビュン走る。
2月は小乾季。毎日晴れて日差しも強いが、朝はまだ半袖では肌寒い。空気がとても乾燥していて、そこらじゅうで埃が舞う。すでに緑色の座席カバーがうっすら茶色のベールをかぶっている。持っている手荷物も、そして車内の人間までも、何もかもがあっという間に埃まみれ。私は日差しというより砂埃を避けるため、サングラスで目を覆う。
アルーシャから南西へ100キロ、「マニヤラ湖国立公園」まで2時間。

しばらく行くと車道の脇に人だかりができている。道行く車が呼び止められる。
「ああ、警察、警察!」
シンバが首を振りながら、腕に巻いた時計を見る。
「朝食の時間だ」
道路の脇に停車すると、がっしりした男性警官がやってくる。前のワゴン車を見ると、婦警がトランクを調べている。彼らは何をしているのだろう。シンバは警官とにこやかに話をし、ポケットからお金を出す。警官はそれを受け取り、行ってよしと合図を出す。シンバがふたたびスワヒリ語で何か言い、車を出す。
警官たちが後ろで小さくなった頃、私はいったい何だったのかと運転席に尋ねてみる。
「警察はいつもこうさ。朝の時間は『朝食をくれ』、昼だったら『ランチをくれ』、夕方になれば『ディーナーをくれ』。ここで払わないと次のとき問題になる。だから払わざるをえないんだ」
タンザニアでは警官の待遇があまりよくないらしく、警官による小銭稼ぎが横行している。むしろこのようなポケットマネーを前提に、やや低めの給料が設定されているとさえ言えるのかもしれない。

車がふたたび道路を走る。サファリカーはトヨタでなくちゃとシンバが言う。リップサービスではなさそうだ。
「サファリカーはだいたいトヨタ。ときどきランドローバーなんかもいるけど、そのうちすぐ壊れるからね。サバンナで故障するとおおごとだろう?」
そういえば、アルーシャでボロボロに使い込まれた日本車を何度も見たのを思い出す。日本ではもう誰も乗らないような状態の、見ているこっちを不安にするほど古めかしい中古自動車。おそらく破格の値段でアフリカに運びこまれてくるのだろう。とうに廃盤になっているトヨタのワゴンやミニバスが、アルーシャの埃っぽい未舗装道路を駆けていく。「旅館 椿荘」。「デイサービス 花の里」。車体に書かれた漢字や仮名が、その出自にかんする生なましい情報を残している。そして車内は超満員。いったいどこへ行くのだろう。色とりどりの民族衣装をまとった人が、まるで積荷か何かのようにぎっしりと詰め込まれている。思わず目を釘付けにしていると、浅黒い肌をした乗客たちがギョロリとした目でこちらを見る。
いくつかの小さな村やマーケットを通過すると、あたり一面視界が開け、サバンナに突入する。乾いた砂。短い草。バオバブやアカシアの木々。
そしてこんなところに誰がいるのと思える場所で、突如姿を現す者がいる。それがマサイだ。

赤い衣、青い衣、紫の衣。どれも一目でマサイのそれと分かる特別な生地。色は年齢によって変わるが、マサイといえばやはり赤だ。そして足元にはマサイのサンダル。この牛皮のサンダルを履き、彼らはどこまでも歩いていく。耳と首には大きなピアスとネックレス。マサイの伝統にしたがって、男は何人もの妻を持ち、1つの家族が1つの集落を形成し、数年単位で家畜とともに移動しながら暮らしている。彼らの多くは経済的にかなり貧しい。シンバによれば日々の食べ物にも困るほどで、マサイの子どもは常にひどくお腹を空かせているという。それは一目瞭然で、マサイたちのほとんどはガリガリに痩せている。大人でも足首がつかめるほど。肌の色とも相まって、脚はまるで枝のようだ。
サファリは通常、朝食後に出発し、次の宿にたどり着くまでほとんどを車内で過ごす。だからお昼のほとんどは宿で積まれたお弁当になるのだが(たいていは紙の箱や袋に入った簡素な食事で、パンやクラッカーにバナナやリンゴ、そしてグリルしたチキンの塊などが入っている)、シンバはかならず残り物をマサイの子どもに取っておく。
「廃棄食品。聞いたことがあるだろう? ここでは大きな問題なんだ」
道路の端に車を停めて、家畜を追うマサイの子どもに「おーい、おーい!」と呼びかけながら、シンバが私にそうつぶやく。